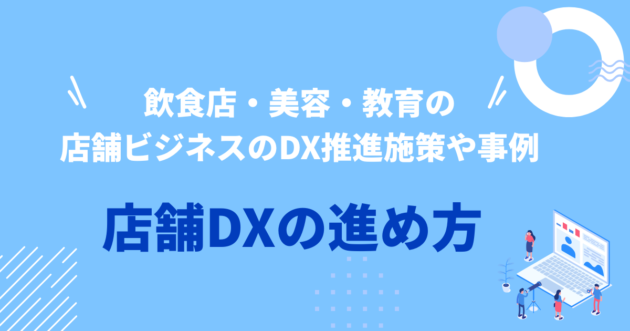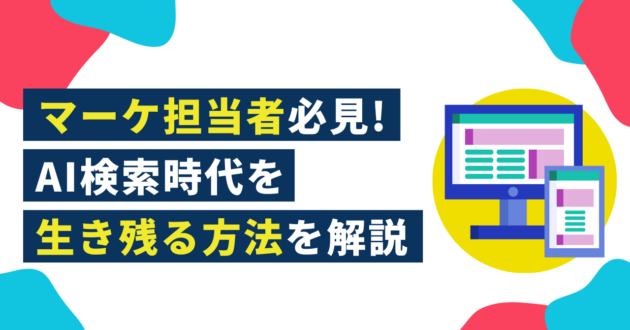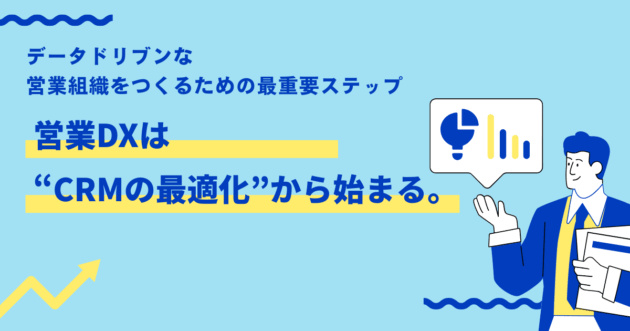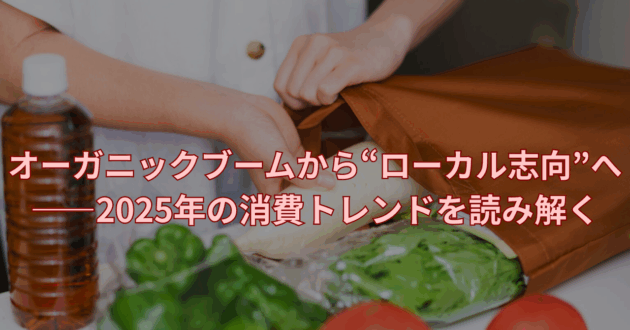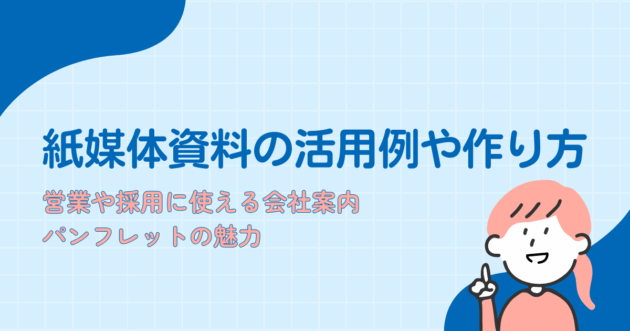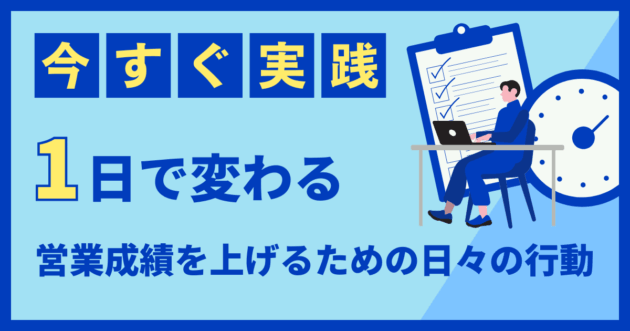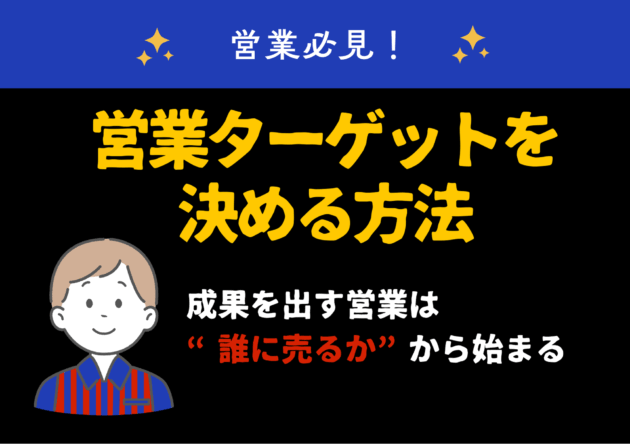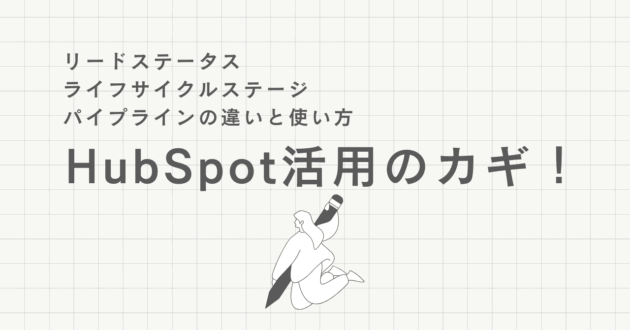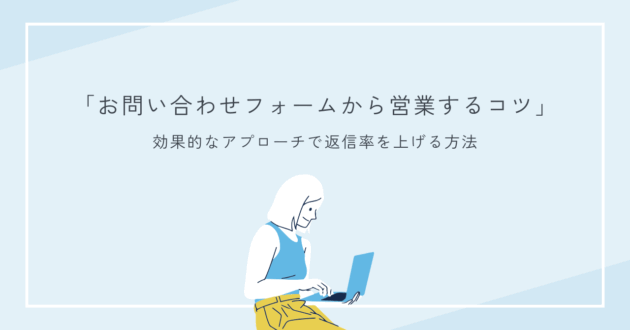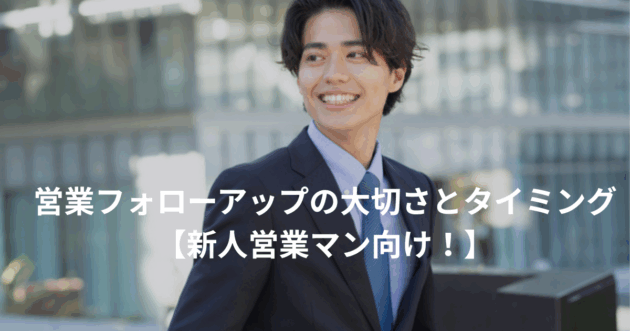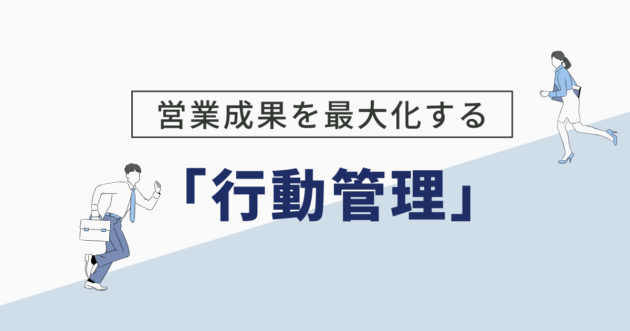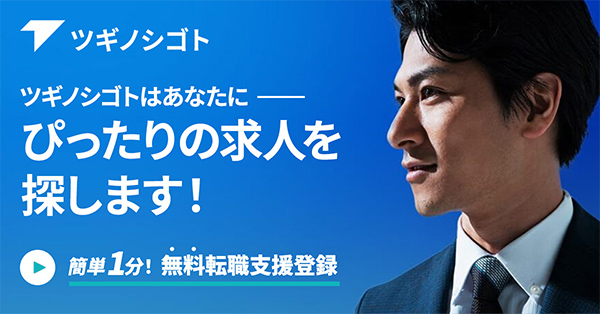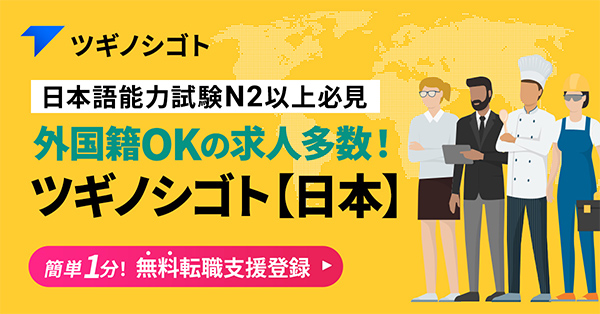2023年10月1日から、広告明示義務ともいえる「ステマ(ステルスマーケティング)規制」が施行されました。広告であるにもかかわらず、第三者の口コミを装って宣伝すると景品表示法違反となり、措置命令や公表といった罰則を受けることになります。
本記事では、ステマ規制で違法になる4条件、規制対象外となるケース、違反したときの罰則を中心に、ステルスマーケティングで実務担当者が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
ステマ(ステルスマーケティング)規制とは?
ステマ規制とは、2023年10月から施行された広告明示義務のルールを指します。広告であることを明示せずに第三者の口コミを装った場合、不当表示として処罰対象になります。
ステマとは、一般消費者に広告だと気づかせないまま宣伝する行為のこと。具体例としては、インフルエンサーや芸能人に依頼して、好意的な感想をあたかも自主的な意見のように発信するケースです。過去の「ペニーオークション詐欺事件」などを背景に、悪質なPR手法が社会問題化し、規制が強化されました。
ステマ規制の運用基準
消費者庁が公表した運用基準(内閣府告示第19号)は次のとおりです。
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」
つまり、事業者が関与した広告表示であるにもかかわらず、それが消費者に広告と認識されにくい場合は、不当表示と判断されます。
ステマ規制で違法になる4条件
ステマ規制では、以下の4条件をすべて満たした場合に「違法」とされます。
- 事業者の表示である
事業者が表示内容に関与している場合、第三者の自主的発信であっても「事業者の表示」とみなされます。 - 消費者が広告と気づけない
表示全体から広告だと判断できない場合に規制対象となります。 - 表示媒体を用いている
Web・SNSだけでなく、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどあらゆる媒体が対象です。 - 事業者(広告主)による表示である
規制対象となるのは広告主自身。インフルエンサーや媒体社は直接の違反者にはなりません。
規制対象にならないケース
次のようなケースは規制対象外です。
- 広告代理店やインフルエンサーが「制作に関与しただけ」の場合
- 新聞社・出版社・放送局など「表示を掲載しただけ」の場合
- 小売業者が「商品を陳列・販売しただけ」の場合
- ECモール運営者が「取引の場を提供しているだけ」の場合
ただし、これらの関係者でも、実質的に広告内容を決定していると判断されれば責任を問われる可能性はあります。
ステマ規制に違反した場合の罰則
ステマ規制に違反すると、消費者庁による措置命令が下され、その内容が公表されます。措置命令の例は以下のとおりです。
- 違反した広告表示の差止め
- 違反内容を消費者に周知徹底
- 再発防止策の実施
- 将来にわたって違反行為を繰り返さないことの確約
この時点では課徴金は科されませんが、措置命令を無視すると懲役や罰金といった刑事罰が発生する可能性もあります。また、優良誤認・有利誤認の表示が含まれる場合は、追加で厳しい措置がとられる点にも注意が必要です。
まとめ:ステマ規制で守るべきポイント
2023年10月に施行されたステマ規制は、広告の透明性を確保し、消費者保護を目的としたルールです。最後に要点を整理しておきましょう。
- 違法となる4条件:「事業者の表示である」「消費者が広告と気づけない」「媒体を用いている」「広告主による表示」であること
- 規制対象外:代理店・インフルエンサー・媒体社・小売業者などが「関与のみ」「掲載のみ」である場合
- 罰則:措置命令・公表によりブランドイメージが毀損、無視すれば懲役・罰金の可能性あり
広告やPRを行う際は、必ず「広告であることの明示」を徹底しましょう。透明性のある発信が、企業と消費者の信頼関係を築く第一歩です。