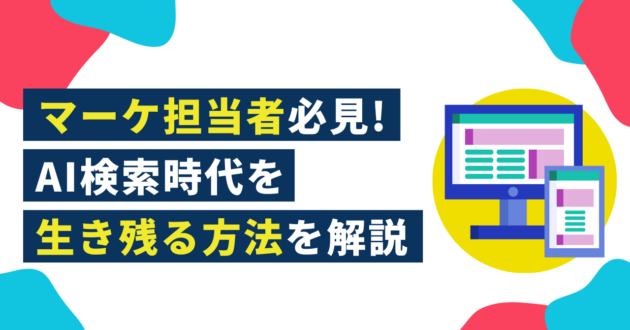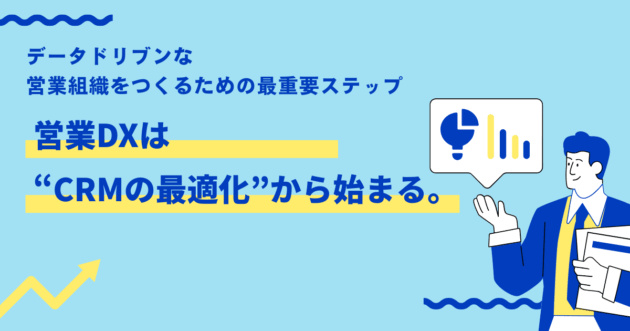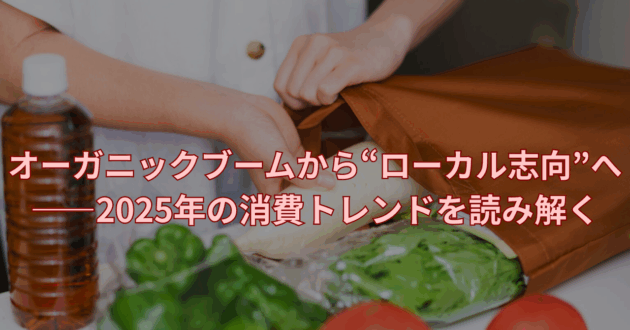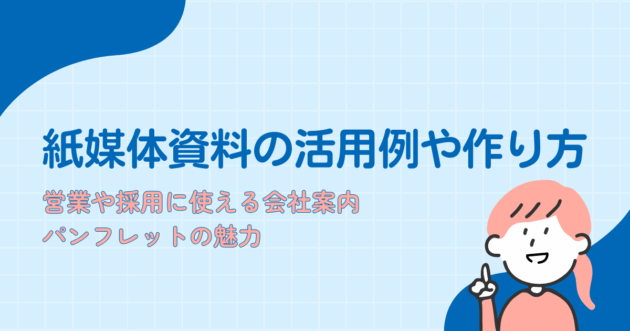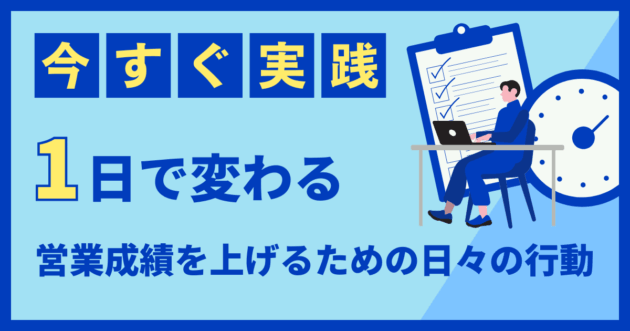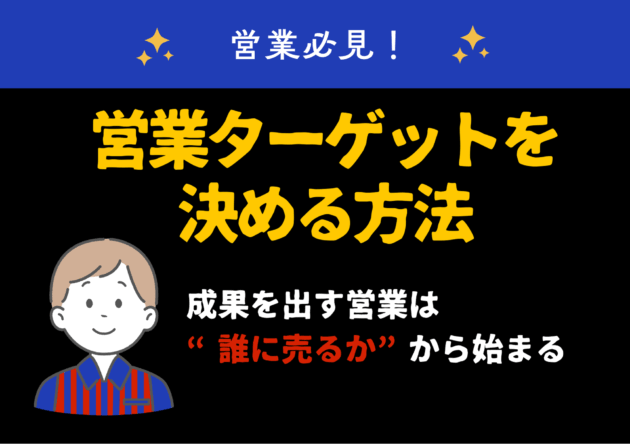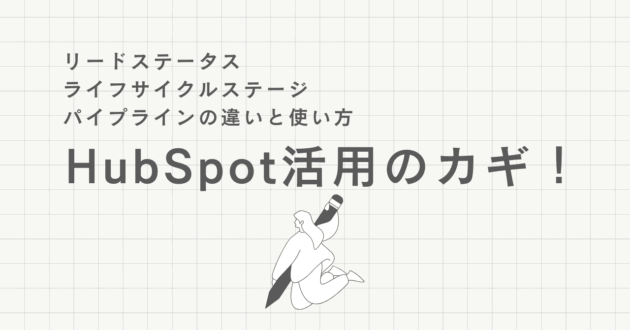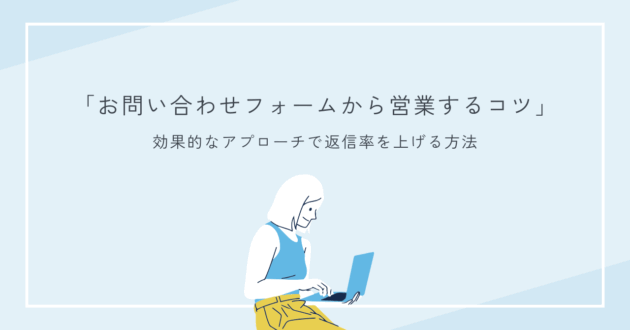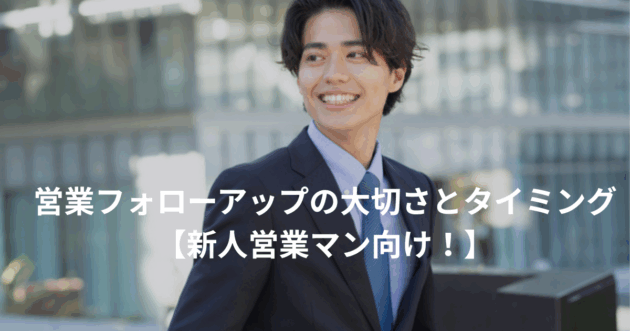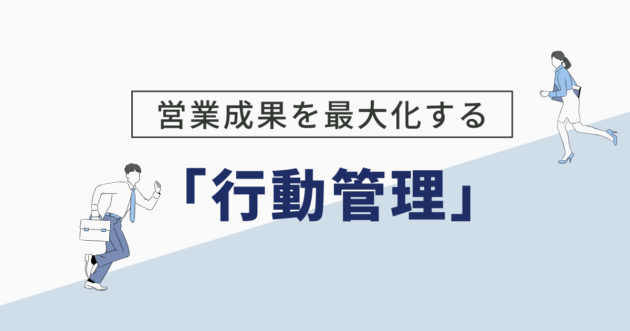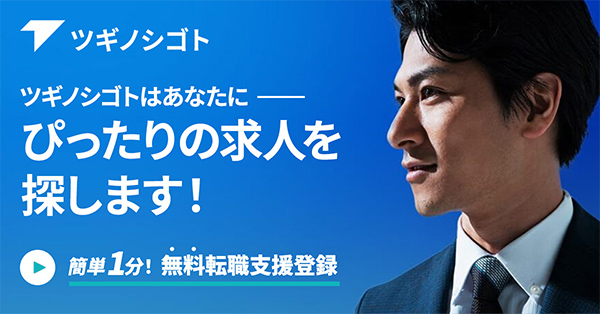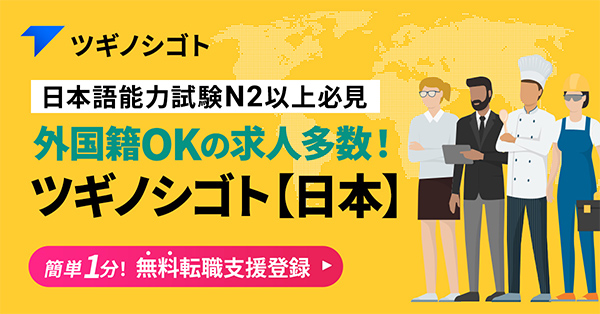デジタル化が進むなか、広告でありながら「広告ではない」ように見せかけたステルスマーケティング(ステマ)が問題となっています。以前から批判されていた手法ですが、SNS時代に入り拡散力が増したことでリスクが高まっています。
本記事では、ステルスマーケティングの具体的な手法から、消費者庁による措置命令の事例、さらに今後の規制動向まで詳しく解説します。
ステルスマーケティングとは?
ステルスマーケティングとは、広告主から報酬を受け取りながら、あたかも中立的な第三者を装って宣伝を行う行為です。一般消費者を騙し、売上向上を図る点で不公正かつ詐欺的と批判されています。
万一「ステマ」が発覚すれば、SNS炎上・信頼失墜・ブランド毀損につながる危険性があります。短期的に売上が伸びる場合もありますが、長期的には極めてリスキーな手法です。
ステルスマーケティングの手法
手法1.一般消費者になりすましてクチコミを投稿
- 人を雇い、ECサイトで「やらせレビュー」を量産
- 企業が自ら一般消費者を装い、自社商品を高評価
- グルメサイトやGoogleビジネスプロフィールで虚偽レビューを大量投稿
手法2.インフルエンサーや芸能人による隠れ宣伝
- 芸能人に報酬を支払い「愛用している」と言わせる
- インフルエンサーに実際には使っていない製品を紹介させる
これらの手法はいずれも消費者を欺くものであり、場合によっては違法行為にあたる可能性があります。

措置命令の事例:アクガレージ&アシスト
消費者庁は、株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社が供給するサプリメントに対し、「豊胸効果が得られる」と誤認させる表示を行ったとして、景品表示法に基づく措置命令を出しました。
- 媒体:ECサイト、インスタグラム
- 問題点:広告であることを隠した表示
- 法的根拠:景品表示法「優良誤認」に該当
重要なのは、日本ではステマそのものを直接規制する法律がなく、不当表示(優良誤認/有利誤認)に該当する場合のみ措置対象となる点です。
規制の動きと今後の展望
消費者庁によれば、OECD加盟国の中でステマ規制が存在しないのは日本のみとされています。ただし2022年には「ステルスマーケティングに関する検討会」が開催され、規制強化の動きが進行中です。
企業がステマを採用することは、短期的な利益と引き換えにブランドを危険に晒す選択です。今後は明示的な広告表記と透明性の確保が求められていくでしょう。
まとめ
- ステマは消費者を欺く不公正な手法
- 炎上や信用失墜など、リスクが極めて大きい
- 日本では景品表示法による一部規制のみ → 今後規制強化の可能性あり
- 企業は透明性ある広告活動を行うべき
ステルスマーケティングは「短期的な売上」よりも「長期的な信頼」を失う危険が大きい行為です。規制動向を注視しつつ、消費者との信頼関係を築く広告戦略を取ることが、これからの企業に求められる姿勢です。