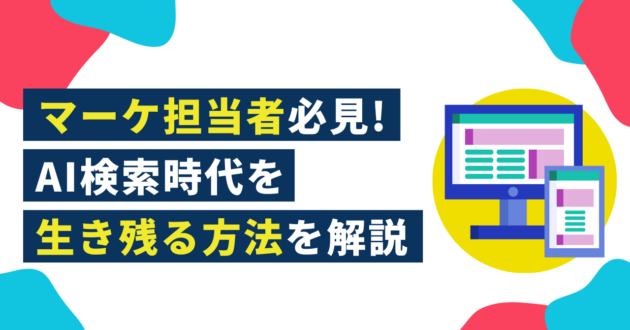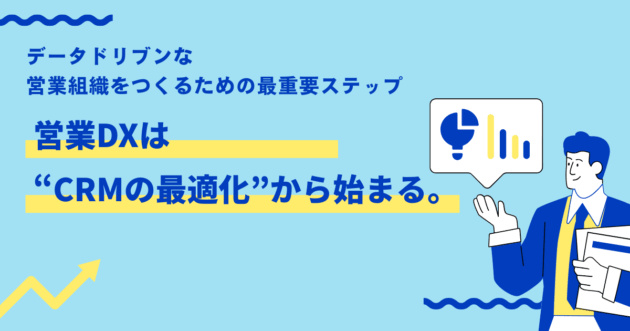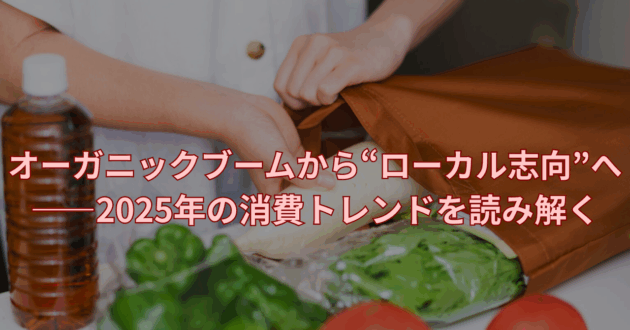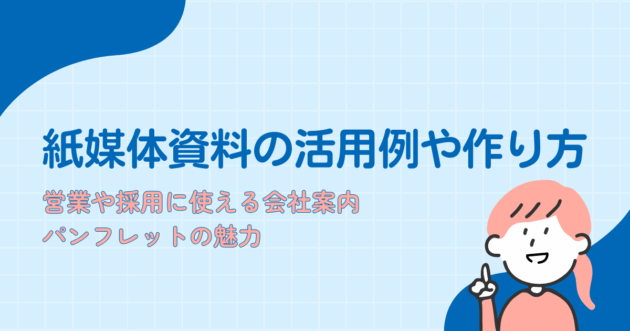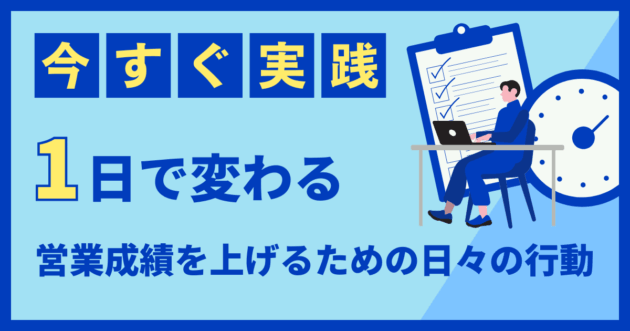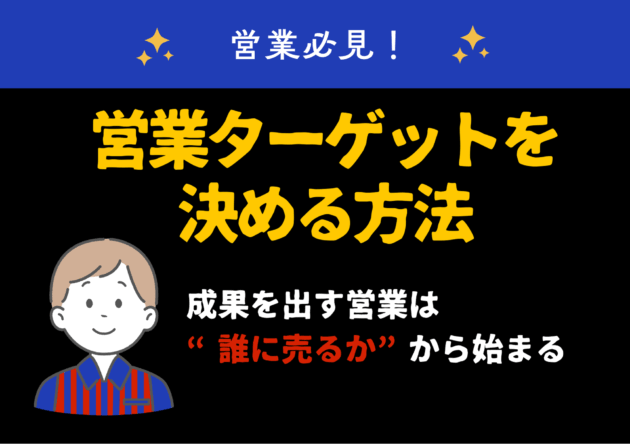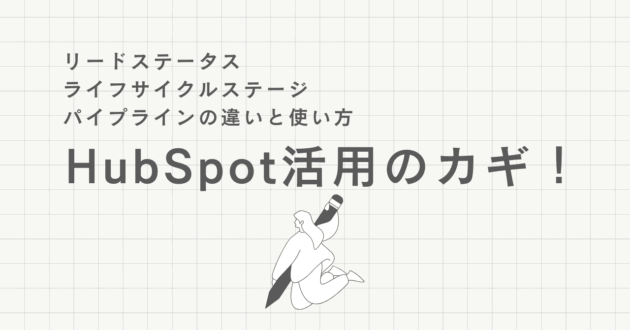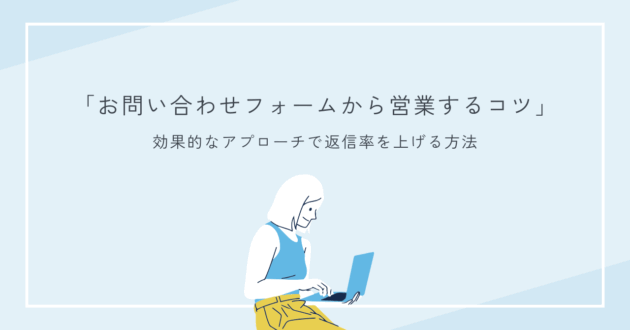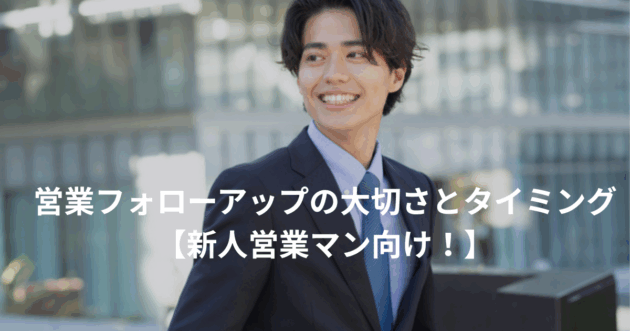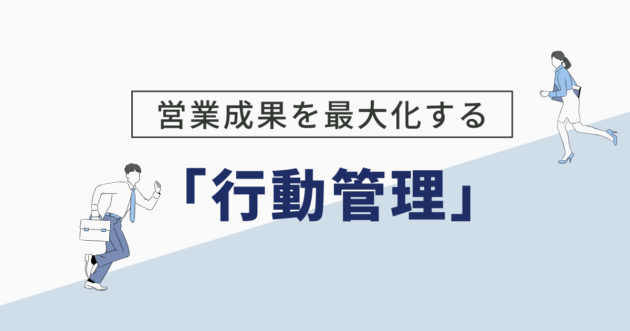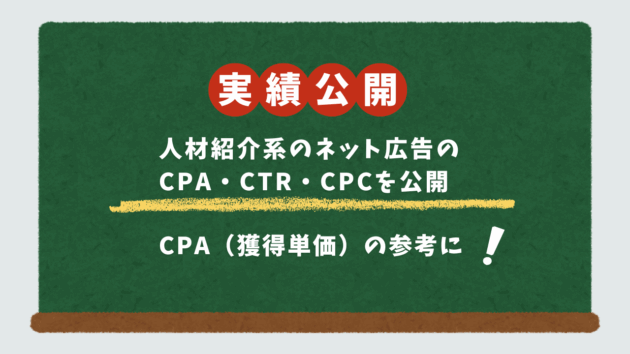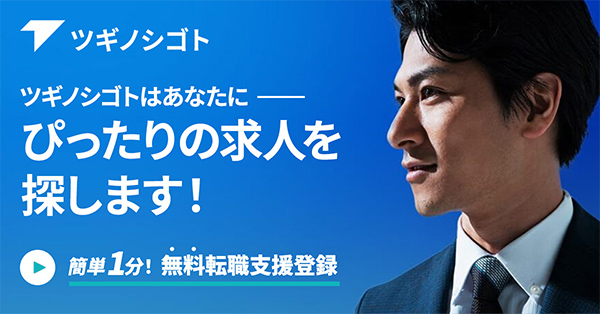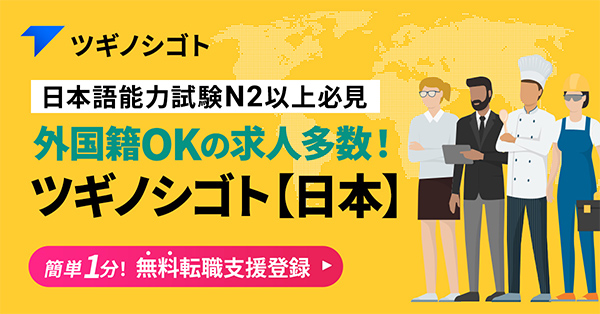「推し活」と聞くと、アイドルやアニメキャラを応援する行動を思い浮かべる人も多いでしょう。
ですが、近年はその意味が大きく拡大し、アーティストやスポーツ選手だけでなく、地域キャラクター、VTuber、さらには企業ブランドや商品にまで「推し」が広がっています。
第2回 推し活実態アンケート調査では、推し活市場は年間3.5兆円以上に成長して、ファン1人あたりの年間支出額は約25万円にのぼるという結果もあります。
消費者は「モノを買う」だけでなく、「推しを応援するためにお金を使う」時代へとシフトしています。
企業にとって推し活は、新しいマーケティング戦略の入口にもなるのです。
推し活市場規模3.5兆円以上の理由とは?
推し活市場規模が3.5兆円以上に拡大した理由は、主に3つです。
理由1.Z世代・ミレニアル世代の消費行動の変化
推し活市場を支えているのは、Z世代とミレニアル世代です。彼らは「自己表現」と「体験」を重視し、モノよりも「好きな存在への投資」を優先します。SNSでの拡散文化もあり、「推しを応援している自分」自体がアイデンティティ形成につながるため、消費行動に直結します。
理由2.デジタルプラットフォームの普及
YouTube、TikTok、Instagram、そしてファンクラブアプリ。これらは推しとの距離を縮め、ファンの熱量を可視化する仕組みを提供しています。オンライン配信ライブやグッズECは、リアルイベントに行けない層の消費を刺激し、結果として市場規模を押し広げています。
理由3.コロナ禍を契機としたオンライン化
コロナ禍は「直接会えない」制約が生まれた一方で、「オンラインで推しを応援する」文化を加速させました。バーチャル握手会や限定配信は、従来のファン活動を一気にデジタルに引き寄せ、市場を拡大させた大きな要因です。
推し活ビジネスのマーケティング・集客施策
施策1.推し活を「消費動機」として設計する
従来の購買行動モデル(AIDMAやAISAS)では必要だから買うのが一般的である一方で、推し活は応援したいから買う「応援消費」が多くなってきます。たとえば、アーティストとのコラボ飲料やアニメとのタイアップ商品は、味や機能ではなく「推しが関わっているから買う」といった心理になりやすいのです。
施策2.ファン参加型のプロモーションを仕掛ける
推し活は一方的な購買ではなく、「一緒に盛り上げる」体験が鍵です。
- InstagramやX(旧Twitter)でのハッシュタグキャンペーン
- ファン投票型の商品開発
- 限定グッズやシリアルナンバーつき商品の販売
こうした仕掛けは、ファンの“布教心”を刺激し、UGC(口コミなどのユーザー生成コンテンツ)としてSNSで拡散されます。
施策3.BPO・人材領域への応用
企業においても、「推したい会社」「推したいブランド」といった心理は存在します。BPO(アウトソーシング)会社や制作会社も、クライアントの“推され方”をデザインする立場として参入余地があるのです。
また人材採用でも、「福利厚生」や「給与」だけでなく、「この企業を応援したい」と思わせるストーリー設計が、応募数を大きく左右します。
推し活ビジネスのマーケティング成功事例
企業における推し活ビジネスのマーケティング成功事例は、主に3つ挙げられます。
事例1.キャラクターコラボ(飲食業界)
カフェやファストフードでは、アニメやアイドルとのコラボメニューが常態化。推しキャラの描かれたカップや限定グッズを入手するために、リピート購入が生まれています。
事例2.ご当地キャラ・観光施策(地域振興)
ゆるキャラや地域限定イベントは、「推し活」を観光誘致(地域活性化)と掛け合わせた代表例です。ファンは“推しの聖地巡礼”として現地を訪れ、消費活動をしてくれます。
事例3.限定コラボ商品(小売・EC)
アパレルやコスメ分野では、人気アーティストやVTuberとのコラボが相次ぎ、発売直後に即完売するケースも増えています。「手に入りにくいものほど欲しくなる」希少性の心理や「推しブランドを身につけたい」推しの心理が、消費者の購買を後押しします。
推し活ビジネスのマーケティング課題
企業における推し活ビジネスのマーケティング課題は、主に3つです。
課題1.ファン心理を理解するマーケティング人材の育成
推し活は、従来のマーケティング理論と異なる点があり、企業内に「ファン心理を読み解ける人材」が必要になります。Z世代のインターン活用や、SNSネイティブな人材採用が有効です。
課題2.短期消費ではなく、長期関係性設計
一時的なコラボではなく、ファンとの長期的な関係性を築くことが重要です。ファンクラブ制度や定期イベントのように、継続的に「推せる場」を提供することがブランド価値につながります。
課題3.倫理的リスクと炎上回避
推し活は熱狂層が多くて、ファンの期待に応えられなかったときに反感を買いやすいです。限定商品の品切れや杜撰な企画進行は炎上につながるため、丁寧な運営と誠実な対応が不可欠です。
まとめ
推し活市場は、単なるサブカル文化にとどまらず、年間3.5兆円以上の巨大産業に成長しています。
企業がこの市場を取り込むには、単発のコラボではなく「ファン心理を理解し、参加体験を提供する」ことが求められます。
そしてこの考え方は、BtoC領域だけでなく、採用やBPO、広告制作などBtoB領域にも応用可能です。
推し活消費を「新しい購買動機」ととらえれば、企業のマーケティング戦略に大きなヒントを与えてくれるでしょう。