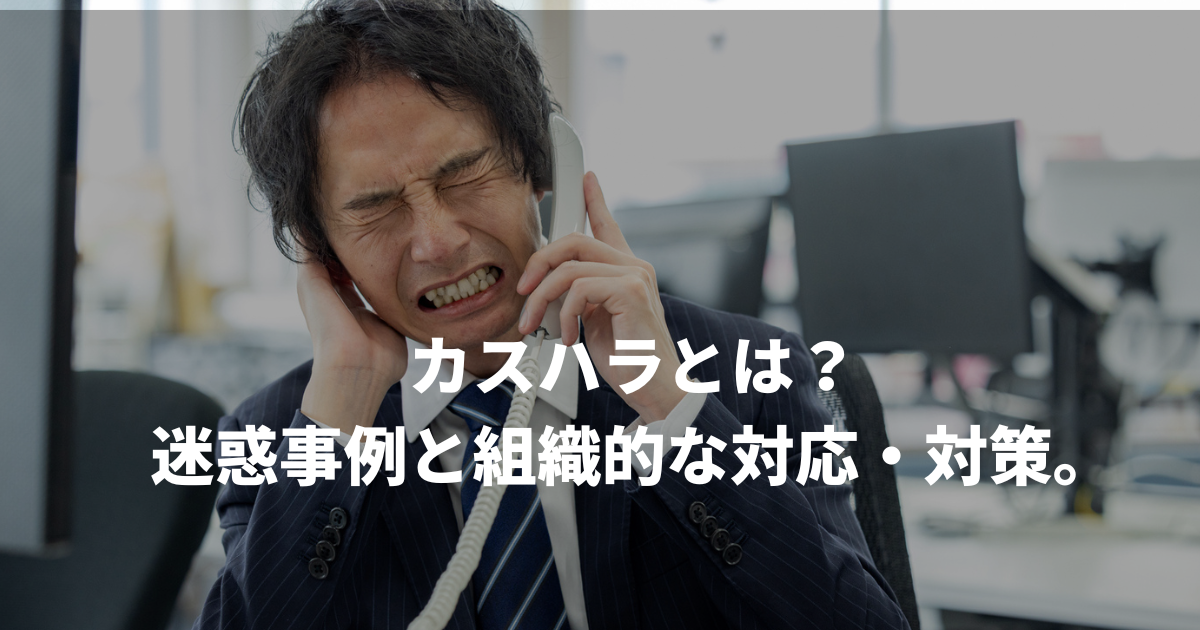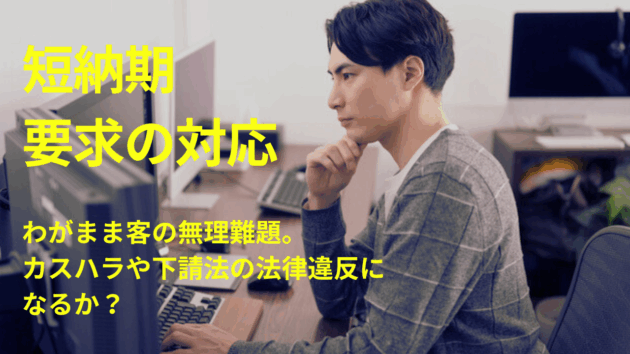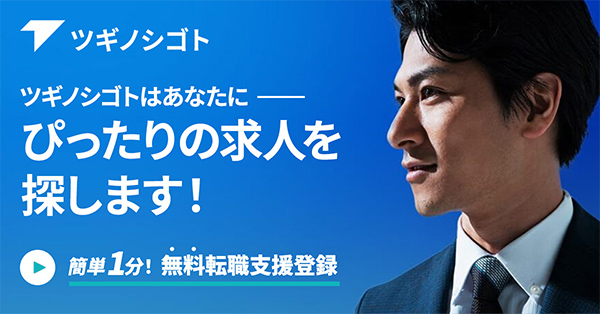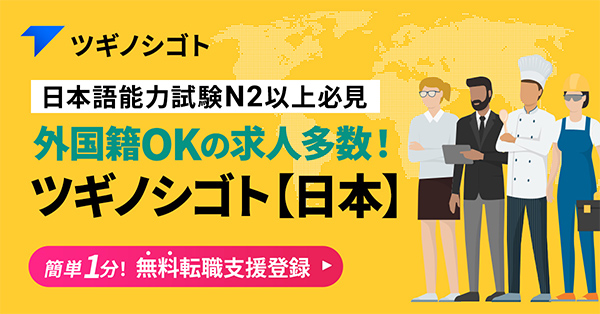最近、お客様や利用者様の言動に、理不尽さを感じることはありませんか?
それは、もしかすると「カスハラ(カスタマーハラスメント)」かもしれません。
お客様という優位な立場を利用して、従業員や店員に対して迷惑・理不尽な言動をとる人がいるのです。
このカスハラを放置すれば、従業員の心身の不調につながり、労災が発生するリスクがあります。
そのような事態を防ぐためにも、会社は、従業員をカスハラから守る仕組みを考える必要があります。
本記事では、カスハラの事例や組織的な対応・対策について、わかりやすく解説していきます。
カスハラ(カスタマーハラスメント)とは
カスハラとは、カスタマーハラスメントの略で、顧客(カスタマー)の嫌がらせ(ハラスメント)を意味する造語です。
よくあるのは、お客様という優位な立場を利用して、従業員や店員に対して迷惑・理不尽な言動をとるといったことになります。
厚生労働省の定義
厳密に言うと、カスハラとは、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、 当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」です。
この定義は、厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf)』に記載されているものになります。
正当なクレームとの違い
「カスハラ」と「正当なクレーム」との大きな違いは、妥当性の有無(正当か不当か)です。
- カスハラ
普通に対応しただけなのに「態度が気に入らない」など、不当な理由で嫌がらせをする - 正当なクレーム
なんらかの不利益(誤出荷や納期遅延)を被り、正当な理由があって対応を要求する
カスハラ(カスタマーハラスメント)の迷惑事例
カスタマーハラスメントに該当する迷惑行為とその事例は、以下のとおりです。
- 精神的な攻撃(暴言・脅迫・侮辱など)
事例:「責任者を出せ」「ネットにさらすぞ」「こんなこともできないのか」などと言う
- 身体的な攻撃(暴行・傷害など)
事例:げんこつをする、髪の毛を引っ張る、唾をかけるなど
- 威圧的な言動
事例:声を荒げる、ドンと物に当たる、にらみつけるなど
- 拘束的な言動
事例:話が異常に長い、営業時間を過ぎても対応を求める、居眠りをして困らせるなど
- 執拗な言動
事例:何度も電話をかけてくる、過去のミスをネチネ言う、ストーカーのようにつきまとうなど
ほかにも、以下のようなカスハラもあります。
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 不相当な金銭要求(返金や値引き)
- 不相当なサービス要求
- 不相当な謝罪要求
なお上記は、あくまでも例であり、これらに限られるものでもありません。
では会社として、従業員の尊厳を守るには、どうしたらよいのでしょうか。
カスハラ(カスタマーハラスメント)の対応・対策
カスハラ(カスタマーハラスメント)への対応・対策として、会社・組織ができることは、主に3つあります。
対応1.カスハラ対策方針の策定
手始めにできることは、コーポレートサイトで「カスタマーハラスメントに対する方針」を公表することです。
従業員の尊厳を守るために、「カスタマーハラスメントの対象行為に該当する場合、毅然として対応する」といった企業のスタンスを記載します。悪質な場合は、「出禁(出入り禁止)にする」「取引停止にする」「警察や弁護士に相談する」など、大まかな方針を立てるということです。
対応2.カスハラ対策マニュアルの作成
『カスタマーハラスメント対策マニュアル』を作成して、顧客による「精神的な攻撃」「身体的な攻撃」などの対処を事前に決めておくことも重要です。
精神的な攻撃の対応
たとえば、顧客が「誠意を見せろ」と言ってきたとき、どう対処するかです。
「誠意を見せろ」と言う顧客は、そもそも自分の要求内容が曖昧だったりします。
そのため、要求内容を具体的に聞いて、常識の範囲内で要求に応えると解決できるケースもあります。
あまりにも気性が激しい場合は、脅迫罪(刑法第222条)に該当する犯罪行為とみなして、法律を盾にとることも可能です。
ほかにも「責任者を出せ」「今すぐ謝りに来い」など、カスハラをする顧客がよく使う言葉があり、そんなとき対応マニュアルがあると心のよりどころになりえます。
身体的な攻撃の対応
たとえば認知症患者や介護利用者が、現場スタッフに暴力を振るってきたとき、どう対処するかです。
このような場合、暴れたときに物理的な距離を取る方法や、相手の自尊心を傷つけない言い方などを社内で情報共有できるとよいでしょう。
また、どういった暴力行為をしたら、警察を呼ぶのかという線引きを明確にしておくことも効果的です。
そもそも職員に対して暴力を振るうのは、基本的に犯罪行為に当たり、暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(刑法第204条)で訴えることもできます。
対応3.カスハラ相談窓口の設置
従業員の孤立防止策として、社内に「カスタマーハラスメント相談窓口」を設置することも効果的です。
とはいえ、いきなり相談窓口を設置するのは難しいと思います。
そのようなときは、まずは「上司」や「人事労務」を相談先にするのも1つの手です。
社内で解決が難しい場合は、以下のような外部の相談先も利用するとよいでしょう。
- ハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業)https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
- 警察
- 弁護士
カスハラ(カスタマーハラスメント)のまとめ
カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客の嫌がらせです。
お客様という優位な立場を利用して、従業員や店員に対して迷惑・理不尽な言動をとったりすることです。
それは、正当なクレームとは違って、妥当性や正当性がありません。
このようなカスハラに対して、会社は毅然として対応する必要性があります。
具体的な対応・対策としてできることは、主に以下の3つです。
- カスハラ対策方針の策定
- カスハラ対策マニュアルの作成
- カスハラ相談窓口の設置
本記事が、「気持ちよく働ける職場づくり」のご参考になれば幸いです。